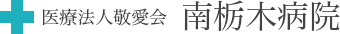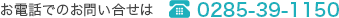リハビリ
理学療法科(PT)
身体に障害のある者に対して、主としてその基本的能力の回復を図るために、治療体操・電気療法・マッサージ・温熱などの物理的手段を加えます。
脳卒中後遺症・骨折後遺症などが対象となります。

作業療法科(OT)
身体又は精神障害の有る者に対して、主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸・工作・その他の様々な作業を行います。
脳卒中後遺症・認知症の進行防止・COPD等の呼吸器患者の肺機能回復を図ります。

言語聴覚療法科(ST)
病気や交通事故後の失語症・聴覚障害・会話能力障害のある者に訓練を行い、自分らしい生活を取り戻す為に、支援し、摂食・嚥下障害の回復を図ります。